めでたき寅年迎春を口実に、このお正月もずいぶんお酒を楽しみ、トラになったことでした。日本酒、ビール、ウイスキー、焼酎から「電気ブラン」までやりましたが、みんなチョビチョビで、トラというよりネコかな(笑)。
そのうち、はじめて体験したお酒――僕がいうところの初物酒を3つ紹介することにしましょう。まず日本酒からは、群馬県川場村・永井酒造の純米大吟醸「谷川岳」――ラベルには次のように書かれています。
群馬県最北部利根川源流に位置する日本百名山の谷川岳(標高1977m)。四季折々の表情を持ち、蔵周辺地域のシンボルの山として愛されております。このお酒は、山に降る豊富な雪や雨が、自然の大地でゆっくりと濾過されたやわらかでほのかに甘い天然水の源水仕込みで醸し上げました。

「谷川岳」は日本酒度+3の程よい辛口、おせち料理との相性が抜群でした。ワインやウイスキーだと、ここであふれるような形容詞が出てくるところですが、日本酒だと「フルーティで旨かった」で終わりです。もっともキョウビ、日本酒ソムリエも洋酒に負けじといろいろな修飾語を使いますが、まだ一般化していないようですね。
この「谷川岳」を選んだ理由は、もう一つあります。何十年も前のことですが、谷川岳に登ったとき、「谷川岳1000回」というタスキをかけ、ものすごいスピードで追い抜いていくおじさんがいました。あとで旅館の仲居さんに聞くと、そのあたりでは有名なおじさんで、すでに990回を越え、近々目標の1000回に達するはずだというのです。
世の中には偉い人というか、信じられない人がいるものだと感心した、鮮やかな記憶もあって、初物酒のトップに「谷川岳」を選んだというわけです(笑)。
きっとネットに出ているはずだと思って検索をかけると、案の定ヒットしました。みなかみ町の森邦広さんという方で、1000回達成のあと目標を「谷川岳3000回」にバージョンアップし、2015年10月31日、奥さんの誕生日に、2826回目を達成したという記事でした。
そのとき何と御年80!! 3000回達成を果たされたかどうかは確認できませんでしたが、高尾山登頂2回という記録しかない僕からみると、天文学的数字のように思われました。『日本百名山』の深田久弥さんでも、2826座は登っていないでしょう。

初物酒の2つ目は、スコッチウイスキー「オールド プルトニー」です。話には聞いたことがありますが、やったのは初めてです。ボトルネックの付け根が、瓢箪みたいにプクッとふくらんでいるのがおもしろく、蓋を開けると華やかな花の香りが鼻孔をくすぐります。さっそく土屋守さんの名著『改訂版 モルトウィスキー大全』を開くと、「複雑なボディに潮の香り漂う、『北の強者』」として208ページに出ています。
大ブリテン島の北端、ウィックという町のプルトニータウンにある蒸留所で、1826年創業とありますから、我らが文政9年、化政文化華やかなりし頃、最初の一滴がポットスチルからしたたり落ちたことになります。
プルトニーというのは、町づくりを推し進めた国会議員のサー・ウィリアム・プルトニーに由来するそうです。さらに町を改良整備したのが、『宝島』や『ジキル博士とハイド』を著わしたロバート・スチーブンソンのお父さんだったと聞けば、スコッチに興味のない人も、ぐっと親しみを感じるようになるのではないでしょうか。
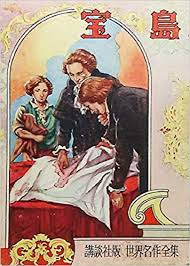
『宝島』『ジキル博士とハイド』といえば、僕にとっては講談社版『世界名作全集』ですね。これまた「日本の古本屋」で検索すると、あの懐かしい装丁の写真とともに出てくるじゃ~ありませんか。『宝島』を即ゲットして読み始めると、小学生のモッチャンに戻った後期高齢者は、もう止められません(笑)。巻末の解説を読むと、プルトニータウンを改良整備したというお父さんについて、次のように書かれていました。
ロバート・ルイ・スチブンソンは1850年に、イギリスのスコットランドの古い都であるエジンバラで生まれました。おとうさんは建築技師で、灯台の建築の専門家でした。おとうさんはわが子のロバートをも灯台建築技師にしようと考えていました。……ロバートは幼いときから、おとうさんの話をきいてそだち、夢の多い少年になりました。
実はこの文章がこれまた懐かしい総ルビなんです。ここでは省かせていただきましたが、総ルビというのは、復活したいすぐれた日本文化だと思います。中国にも総ピンインはありますが、アルファベットなんですから……。総ルビにすれば、「改ざん」「ねつ造」「そん度」「まん延」「ひっ迫」「ら致」「だ捕」みたいな表記を、何と申しましょうか――これも若い人には通じないでしょうね(´艸`)――居心地の悪い書き方をやらないですみます。
もっとも「そん度」は使用頻度が多いためか、もっぱら「忖度」が使われるようですが……。それにしても、「改ざん」「ねつ造」「そん度」「まん延」「ひっ迫」「ら致」「だ捕」と、交ぜ書きになる名詞には、どうしてマイナスイメージが付きまとっているのかな? これらの問題を真剣に考えかつ悩むと、「憂うつ」になるせいかな(笑)。
この交ぜ書きが地名になると、ひどく恥ずかしくなり、やめてくれ~といった感じになります。國華社のある「築地市場」の次は「勝どき」――美味しい飲み屋さんがいっぱいあるのに、もう行く気にもなりません。
ヤジ「白々しいウソを言うな!!」
ロバート・スチーブンソンはエジンバラ大学の工学部に入学したものの、もともと体が弱かったため法律学へ転向しました。そして卒業後は病気をやしなうため、温かい国を旅行したり、お父さんと一緒に船に乗り、大西洋の島々をめぐったりしたそうです。やがて小説家として成功を収めることになるのですが、お父さんの影響がとても大きかったことをはじめて知りました。
ヤジ「そもそも『宝島』なんて、銘スコッチ『オールド プルトニー』とまったく関係のない話じゃないか!!」
しかし実はあるんです。スチーブンソンは執筆に疲れると、お父さんの住む『オールド プルトニー』の故郷ウィックにやってきて、休暇を楽しみつつ構想を練ったそうですから……。
地図を見るとウィックという町は、スコッチのメッカともいうべきスペイサイドのさらにずっと北、オークニー諸島に近いところです。いま東京も寒いですが、ウィックはこんなもんじゃ~ないんでしょうね――あたり前田のクラッカー!!
僕は華やかな花の香りを感じるだけでしたが、土屋守さんは香りも、味も、フィニッシュもみんな「オイリー」だと書いています。オイリーというのは、ときどきウイスキーの形容に出てくる表現ですが、ウイスキーが油っぽいというのはどうもよく分りません。
ところが、スコッチの香りを円グラフみたいにした「ノージングサークル」というチャートが、『改訂版 モルトウィスキー大全』の巻末に載っています。
そのアルデヒド系(フローラル)のなかに、「ラベンダー」や「ハーブ」と一緒に「アマニ油」や「ユーカリ油」があげられ、ワイン様(ワイニィ)には「アーモンドオイル」があります。オイリーというのは、これらを指すものなのでしょうか。
ちなみに「アマニ油」の隣には「ダンボール」があげられ、そのほか「漁船のロープ」「磨き粉」「ゴム臭」なんていうものもあります。しかしそんな臭いウイスキーを好む人が、この世にいるものでしょうか?
いや、いるんでしょうね。僕が大好きな肴にクサヤがあるんですから!! しかしキョウビ、この絶品にクレームをつけるお客さんがいるらしく、出してくれる飲み屋がメッキリ減ってしまいました。
ウィックはかつてニシン漁で栄えた町とのことですが、もちろん訪ねたことはありません。同じくニシン漁で栄えた小樽なら行ったことがありますので、その美しすぎる雪の夜を思い出しながら、「オールド プルトニー」を堪能したことでした。

初物酒の3つ目は地ウイスキーの「戸河内」です。戸河内とは、残念なことに平成の町村大合併によって消滅してしまった広島県の小さな町の地名、現在は安芸太田町というそうです。鉄道計画が頓挫したため使われなくなった大きなトンネルがあり、そのなかでモルトを熟成させるので、その場所がブランド名になったようです。造っているのは広島県廿日市市にあるサクラブルワリーアンドディスティラリーという会社です。
地ビールならぬ地ウイスキーも各地で頑張っていることを知り、いくつか飲んだことはありますが、「戸河内」は初体験です。僕がやった「戸河内」は8年物でしたが、クセのないブレンディットウイスキーで、スッキリとしているのにバニラのようなかすかな甘みも感じられ、これまた「イクサレント!!」でした。
それとともに深く心を動かされたのは、モスグリーンのしゃれたラベルに、パスカルの『パンセ』から一条を引用するというウィットです。第2章「神なき人間の惨めさ」の71「過量、または過少の酒」という条だそうで、パスカル先生曰く……
「酒を与えないと人は真理を見出せない 与えすぎても同様」

おまけに電気ブランのことを少々。「神谷の電気ブランデー」は、昭和初期の頃より「神谷バー」のお客様を中心に親しみを込めて「電気ブラン」と呼ばれるようになりました。「電気ブラン」はブランデーをベースにジン、ワイン、キュラソー、ハーブなどがブレンドされていますが、その配合だけは秘伝となっています。
去年の暮、朝日新聞の「はじまりを歩く」シリーズで、大きく見開き2面を使って神谷バーと電気ブランが取り上げられ、懐かしさのあまりスクラップブックに収めたことでした。かつて「電気ブラン」を飲んだことのほかに、記事に載っていた4代目の神谷信彌さんにお会いしたことがあったからです。
先日も登場してもらった友人の和田泰昌さんから求められ、浅草ロータリー倶楽部で「日本絵画の真贋問題」というトークをやったことがあります。そのとき和田さんから紹介されたのが、英国紳士と見紛う神谷信彌さんでした。
去年の暮、河合正朝さんと、僕もずいぶんお世話になった講談社の斎藤裕子さんの3人で、浅草の「百八つ」という河合さんお馴染みの洒落た焼鳥屋さんでしばらくぶりに飲みました。そのとき二人を待たせ、僕は一人で神谷バーへ急ぎ、「電気ブラン」の小瓶を求めてきたんです。
帰宅して一杯やれば、昔の「電気ブラン」そのまま――いよいよもって懐かしさがこみ上げてきました。
箱の説明には、旧き良き文明開化の時代に思いをはせながら、ストレートで楽しんでいただきたいとあります。しかし40度のストレートはチョットきつく、水割りなどという軟弱な飲み方になってしまったのは、ひとえに後期高齢のせいです。神谷信彌さん、どうぞお許しください!!(笑)
今は30度のもありますが、電気ブランが明治時代に誕生したころは45度あったそうで、文明が発達すると人間は酒に弱くなるという持説(!?)が、いよいよ証明されることになりました。神谷バーでは、午後9時近くになると、閉店を知らせるショパンの「別れの曲」が流されるそうです。これは信彌さんが愛した曲だったとのこと、僕も電気ブランをやりながらぜひ聴いてみたい――河合さん、コロナ第6波が終ったら、今度は神谷バーで!!
朝日新聞の記事には、萩原朔太郎が神谷バーで詠んだ心に沁みる一首が引かれています。
一人にて酒を飲み居れる憐れなるとなりの男なに思ふらん
この記事をまとめたのは、去年「まちの記憶 蒲田」で紹介した小泉信一編集委員で、となりの男とは朔太郎自身の姿だろうと書いています。まさに正鵠を射る読みです!!
だからこそ、若山牧水の「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり」と相前後して詠まれていることが、とても興味深く感じられるんです。「一人にて……」は1913年の朔太郎歌集「ソライロノハナ」に、「白玉の……」は1911年の牧水歌集「路上」に収められているんですから……。
続いて年明け、朝日新聞の「いいね!探訪記」シリーズに「牛久シャトー」が取り上げられました。この本格的ワイン醸造施設も、「電気ブラン」を発明した神谷傳兵衛が開いたものでした。明治36年(1903)のことだそうです。
浅草に神谷バーを開き、電気ブランで成功した傳兵衛さんのつぎの夢が、葡萄栽培、醸造、瓶詰めまでを国内で完結する本格ワイナリーでした。牛久に120ヘクタールの原野を購入し、娘のお婿さんをフランスのボルドーに留学させたそうです。
しかし残念なことに、牛久傳兵衛ワインは電気ブランのようにうまくいかなかったようです。戦後、ワイン造りは規模を縮小せざるを得なくなりました。傳兵衛さんの試みが早すぎたのでしょうか。そのうちフランスから本場のワインがどんどん入ってくるようになりましたから、高度成長時代の日本では、チョットくらい高くっても、やはりお仏蘭西の方がよかったのかもしれません。
朝日新聞の記事はつぎのように〆られています。
2018年、運営会社が事業撤退を発表し、その後、市が第三セクターを立ち上げて運営に乗り出した。牛久産ブドウを使ったワイン製造も再開し、今年初夏の出荷を見込む。木本さん(牛久市文化芸術課)によると、復活するワインの味は、軽やかで渋みが利いたものになりそうだ。
売り出されたらぜひ試飲したいと思います。神谷傳兵衛さんの苦労をしのび、牛久ワイン復活をことほぎながら――今回だけは、「日本のワインは赤玉ポートワインと蜂葡萄酒に尽きる‼ ほかのは飲むに値せず」という持論にこだわることなく……(笑)

