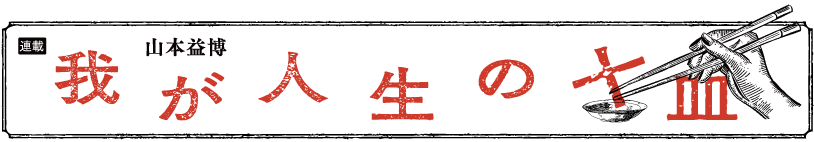東京の握り鮨が誕生したのは、文政元年あたりと言われ、今からちょうど200年前と言うことになる。華屋與兵衛は上方の鯖すし、バッテラに代わる小ぶりな握り鮨にふさわしい魚を探していたのだが、煮ても焼いても生で食べても美味しくないこはだが、酢と塩で締めると、酢飯とぴたりとあうすし種であることを発見する。このこはだの握りを鮨桶に入れて町中を売り歩き、たちまち評判が立ち、2,3年後には両国に店を持つまでになった。
江戸の美意識は「粋」とよく言われるが、江戸っ子は鮨のこはだを好み、着物の小紋を愛でるように、なんでも小ぶりなものがお気に入り。「粋」でなく「小粋」なのである。大仰で大袈裟なものは、「野暮」と言って敬遠した。
「江戸前」の握り鮨では「こはだ」が最古参にして、最重要のすし種にもかかわらず、近年、その主役がすっかり交代してしまっている。いまや「おおとろ」と「うに」が一大人気で、産地名ばかりか、まぐろなど豊洲の仲卸の名札を添えて、お客に提示する店まででてきた。「こはだ」が話題になるのは、夏の「しんこ」の時期のみで、握り一貫にこはだの稚魚しんこを3枚、4枚、中には5枚並べて握って見せ、初物を珍しがる客に振舞うときぐらいである。

今、東京どころか日本中の評判になっている鮨屋を軒並み訪れているのだが、気になることがいくつもあるので、ここに箇条書きしてみたいと思う。
1. 鮨をつまむのに、昨今は「つまみ」と「握り」がセットになった「おまかせ」が幅を利かせ、客が好きなものを注文して鮨をつまむ「お好み」がほとんど姿を消してしまった。
2. 「つまみ」には吟醸酒はじめ数多くの清酒が用意されているが、お茶に無関心な鮨屋が多い。握り鮨にはお茶が一番相性がよいのに。
3. すし種にやたらと庖丁を入れることが多い。美味しくするために入れる庖丁を「隠し庖丁」と言い、見栄えをよくするための庖丁は「飾り庖丁」と呼ぶ。すし種に施された庖丁のほとんどは、インスタ映えする「飾り庖丁」で、食べる前に魚が刻まれて、噛む喜びがない。以前、イタリア料理界の巨匠マッシモ・ボットゥーラは、「次郎」であわびやたこを食べたとき、鮨には「噛む文化」があると称えていた。赤貝やたこに隠し庖丁を入れるのならばまだしも、まぐろにも細かく庖丁を入れるものだから、赤身を食べても舌の上ですぐに溶けてしまう。これでは、もはや、赤身とは呼べない。
4. 握った鮨をつけ台(カウンター)におく際、「大間のまぐろです」「大分の車海老です」などと産地名を添える。以前は、こんなことはなかった。客から聞かれれば、すし職人が「赤貝は閖上です」と答えてくれたものである。客のブランド嗜好がこんな風潮をもたらしてしまったのではなかろうか。
5. 「おおとろ」「うに」が人気と言うことは、脂ののった魚が人気の的である。そのため「のどぐろ」「金目鯛」が幅を利かせているが、「さば」でも脂がのりすぎているものは、酢締めの「〆さば」にするより「さばのみそ煮」のほうがよく似合う。たまに「金目鯛」を昆布締めにして、味を引き締めて握るところはあるが、炙って握るなどと言うことは論外である。
6. はまぐりやあなごの上に塗るソースのことを「つめ」と言う。あなごの煮汁を煮つめていったところから「煮つめ」とよび、それが通称「つめ」となったのだが、これを「甘だれ」と呼ぶすし職人がいる。情けない。
7. 握り鮨をつまんだ最後に、「赤だし」「味噌汁」をだす鮨屋が多い。サービスのつもりだろうが、せっかく鮨を楽しんだあとに、口の中が味噌の香りになってしまうのは、まっぴらごめんである。
8. すし職人のことを「大将」と呼ぶ。本来、職人の頭は「親方」である。「大将」は関西の割烹の料理人の頭の愛称で、それが関東に伝わって、いまでは、何処の鮨屋も「大将」ばかり、言われて気分がいいのか、「親方」と呼んでくださいと返すすし職人もいない。
まだまだ挙げるとキリがないので、やめるが「江戸前」も地に落ちたものである。
「すきやばし次郎」の小野二郎は、これまで数々の「握り鮨」の改革を成し遂げてきた。
● まぐろから握っていたものを、淡泊なものから濃厚なものへと、「白身」から握るようになった。
● そして、握りをそれまでは二貫だったものを一貫ずつ握り、「おまかせ」コースを生み出した。
● 車海老を朝、湯がいていたものを、客の注文を受けてから茹でるようになった。
● かつおは藁で炙った後、氷水につけるのではなく、短時間冷凍庫でかつおを冷やす手法を生み出した。
● たこを1時間揉むことで、香りと味わいを豊かにさせた。
● いくらを秋の旬に大量に急速冷凍させ、一年中、「おまかせ」コースに登場させることを可能にした。
すぐに思いつくだけでこれだけのものが挙げられる。

こうした中で、「すきやばし次郎」のすし種の中心にあるのは、いつも「まぐろ」と「こはだ」である。
「まぐろ」は昔から「脂」より「香り」を大切にして、その種のまぐろを競り落としてくる仲卸の「藤田」のまぐろを使っている。
「こはだ」は「まぐろ」以上に気を遣う、と二郎さんは言う。
いつだったか、営業が始まる前に店に出かけたとき、二郎さんにお勝手に来るように手招きされたことがある。なにかと調理場に顔をだすと、このこはだを食べて見て欲しい、と言うので、つまんでみると、重油臭いこはだだった。
「こはだってやつは、生じゃわからない、酢締めにしてはじめて味がわかる厄介な魚なんです」と言って、酢締めにして仕上がったこはだを全部ゴミ箱に捨ててしまった。
「次郎」で最も大切なすし種は、間違いなく「こはだ」なのだという。
私はとても訊けなかったことなのだが、いつだったか若い女性客が「二郎さんは、ご自分で握られる鮨の中で、一番お好きなお鮨は何でしょうか?」という質問をした。
「こはだ」と言うのが二郎さんの即答だった。
「次郎」では、酢と塩で締めたこはだを3日経ってから握る。味がなじんだこはだが、酸度が強いが、それでいてまろやかな酢めしで握られると、誰しもが夢見心地になる。小野二郎現在95歳、いまだに毎日「すきやばし次郎」のつけ台に立っている。

[連載一覧]山本益博・我が人生の十皿
・01 東京「たつみ亭」荒木保秀の「上かつ」
・02「みかわ是山居」早乙女哲哉のはしらのかき揚げ
・03 東麻布「野田岩」の筏の蒲焼
・04 銀座「すきやばし次郎」のこはだの握り
・05「吉い」吉井智恵一 鱧のお椀
・06 東京「コートドール」斉須政雄の「しそのスープ」
・07 気仙沼「福よし」村上健一のさんまと吉次の塩焼き
・08 柏「竹やぶ」阿部孝雄の そばがき
・09 三ノ輪「トイ・ボックス」山上貴典の醤油ラーメン
・10 京都「浜作」森川裕之の「鯛のお造り
・11 別皿 東京「HIDEMISUGINO」杉野英実の「ランブロワジー」